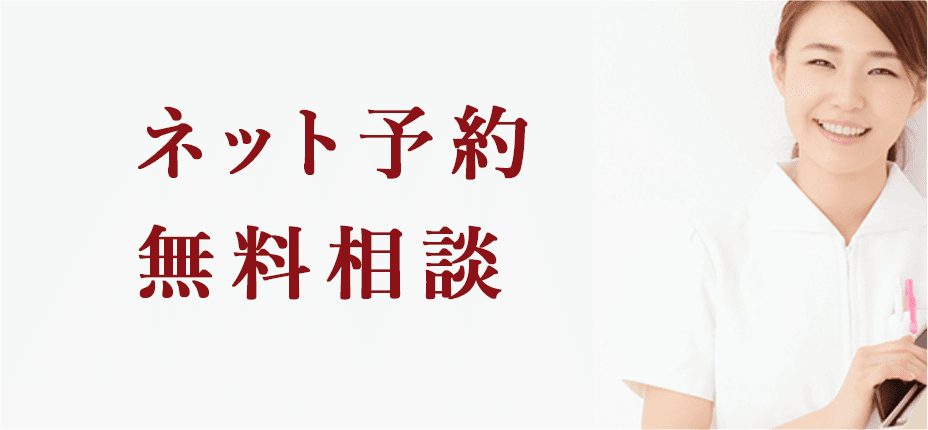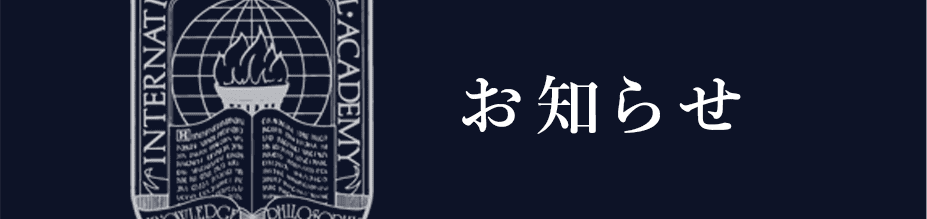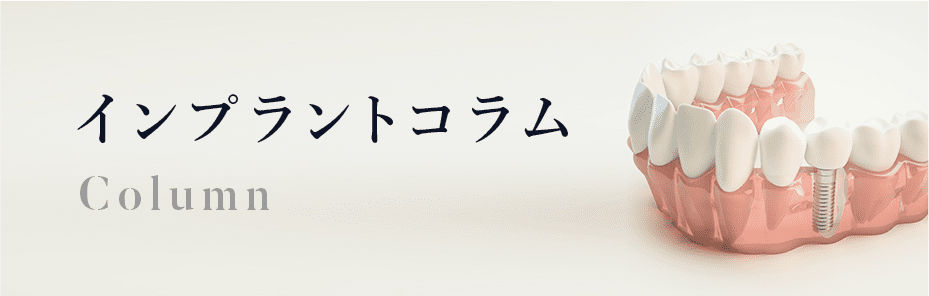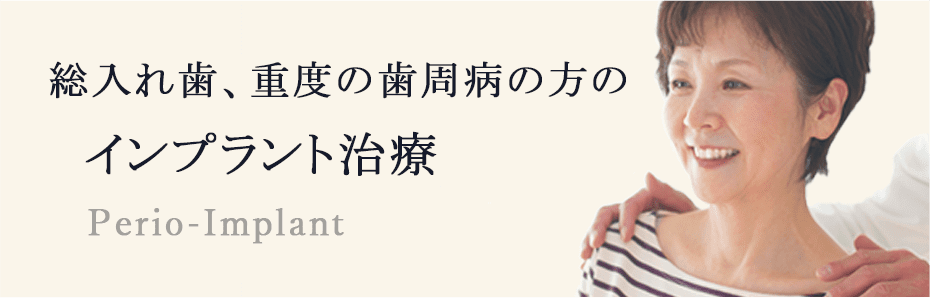インプラントコラム
COLUMN
歯を失うリスクがある歯周病の進行とセルフチェック方法
25.01.29
歯周病は、初期の段階では歯ぐきの腫れや歯磨きの時の出血など、30代以上の方の多くが生じる症状ですが、症状が進行すると顎の骨を溶かし、歯がグラグラする場合もあります。
歯を支える骨の大部分を失ってしまうと、しっかり噛むことができず、抜歯が必要な場合もあります。
大切な歯をいつまでも維持するために歯周病の進行とセルフチェック法について詳しくご紹介します。
歯周病とは

歯周病は、汚れの中にひそんでいる歯周病が原因で発症する細菌感染症です。
進行性の疾患で、一般的には歯肉炎の状態から始まり、進行すると歯周炎に移行します。
歯肉炎の状態は、直接の原因である歯周病菌がひそんでいる磨き残しを除去し、お口の中を清潔にすることが大切です。
歯周病の進行度
歯肉炎の状態
歯周病の初期の段階で、歯ぐきにのみ炎症が生じている状態です。
顎の骨は破壊されていないため、歯石や歯垢を除去して、清潔な口内環境を維持することで症状が改善します。
お子様や若い方でも起きる可能性があります。
症状
強い痛みなどの症状は少ないですが、歯ぐきが腫れたり、歯磨きの時に出血したりする場合があります。
粘膜に炎症が起きているので、ピリピリする感じが出ることもあります。
放置していると症状が進行するため、この段階で改善すると治療期間や治療費用の負担を軽減できます。
治療法
顎の骨が減少しているわけではないため、適切な治療とセルフケアを継続していただくと、元の状態に戻すことが可能です。
・ブラッシング指導
歯が重なっている部分や歯と歯の間などは汚れが残りやすく、歯周病菌が増殖します。
汚れが残っている部分の磨き方や磨きにくい所の汚れの落とし方をブラッシング指導で確認し、毎日のセルフケアに役立てていただきます。
・適切なセルフケア
毎日のセルフケアは、歯磨きが基本ですが歯磨きだけでは6割程度しか汚れを落とすことができないといわれています。
汚れが落としきれない部分は、デンタルグッズを併用して汚れを落としましょう。
歯と歯の間はデンタルフロスや歯間ブラシを使いましょう。
歯が重なっている部分は、毛束が1つになっているタフトブラシを使うと細かい部分の汚れを落としやすくなります。
デンタルグッズ選びに迷った時は、当院でもお口の状況に合わせてご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
・スケーリング
歯垢は時間が経過すると、硬い歯石になります。
歯石になると、歯ブラシでは落とすことができず、歯科医院でのスケーリングが必要です。
歯石をそのまま放置すると、ザラザラしているため、歯垢が付きやすくなります。
定期的な検診でスケーリングをして除去できますので、お口の中に不具合がないかとスケーリングを行いましょう。
軽度歯周炎
歯肉炎を放置すると、歯ぐきの炎症が進行して歯周炎になります。
そうすると、歯ぐきの炎症が強くなり、歯周ポケットが深くなります。
歯周ポケットは、酸素が少なく歯周病菌が好む環境のため、歯周病菌が増殖しやすい状態です。
治療法
・スケーリング
歯の表面に着いた歯石や歯垢を専用の機械で除去します。
・スケーリング・ルートプレーニング(SRP)
歯周ポケットが深くなるとその部分に汚れが入りこみ、歯周病菌が炎症を引き起こすため、専用の器具で丁寧に除去します。
歯周ポケットの深さによっては、麻酔をして行うこともあります。
中等度歯周炎
歯周病が進行して、さらに顎の骨が破壊されている状態です。
歯ぐきの炎症が強くなり口臭が強くなったり、歯がグラグラしたりすることもあります。
治療法
スケーリングやスケーリング・ルートプレーニングに加えて歯周外科治療を行う場合もあります。
歯ぐきを切開し、直接歯石や歯垢などの汚れを除去して根面をきれいにします。
重度歯周炎
顎の骨が半分以上破壊されて、歯がグラグラして食事をすることが難しくなります。
治療法
歯がグラグラして噛むのも難しい状況だと、歯周外科治療を行う場合もありますが、抜歯が検討されることが多くなります。
歯周病のセルフチェック法

チェック1 歯ぐきを鏡で観察
正常な歯ぐきはピンク色で引き締まっています。
一方、歯周病の歯ぐきは赤みを帯びていて、ぶよぶよして腫れている場合もあります。
チェック2 歯磨きの時の出血の有無
通常は、歯磨きの時に出血することはありませんが、歯ぐきが腫れていると歯ブラシが当たる程度の刺激で出血します。
チェック3 口臭の有無
歯ぐきの炎症が強くなると、出血や膿などを伴うことがあり、口臭の原因になります。
また、歯石や歯垢がついたままになると、口臭を引き起こすこともあります。
チェック4 歯ぐきに違和感がないか
歯を支えている歯周組織に炎症があると、歯が浮いた様な感じや重い感じになる場合もあります。
チェック5 歯のぐらつきがないか
歯周組織に炎症が起きると、歯を支える骨が少なくなってしまい、歯がグラグラしてくることがあります。
歯周病予防のためのケア
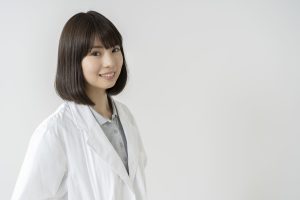
歯周病は自覚症状も少ないため、気づかない間に進行していることも少なくないため、ケアをして予防していくことが大切です。
-
毎日のセルフケア
歯周病の予防の基本は、歯周病菌がひそむ汚れを丁寧に除去することです。
そのためには、毎日の丁寧なセルフケアが欠かせません。
-
定期的な検診
毎日セルフケアしていても、苦手な部分や磨きにくい所は汚れが残ってしまいがちです。
その部分は、定期的な検診のスケーリングで除去します。
定期検診では、むし歯や歯周病の有無、汚れがついている部分の落とし方なども確認します。
毎日のセルフケアと定期的な検診で汚れを落として、きれいな口腔内を維持しましょう。
-
禁煙
たばこに含まれるニコチンは、血管が収縮する働きがあり、酸素が十分に供給されにくくなります。
そうすると、免疫力が低下して歯周病が悪化しやすくなります。
また、口の中が乾燥しやすくなり、細菌が感染しやすい環境になるため、歯周病菌によって好条件になってしまい、歯周病のリスクを高めてしまいます。
歯周病予防のためには、禁煙をおすすめしています。
【まとめ】
歯ぐきが腫れる・出血するなどの症状がある場合は、早めに受信することをおすすめします。
また、大切な歯をいつまでも維持するために、日頃からセルフケアや定期検診を受けて歯周病を予防しましょう。