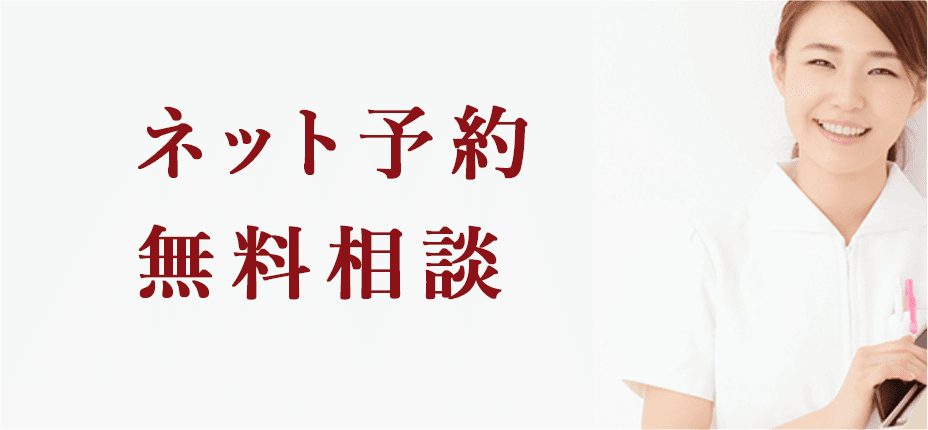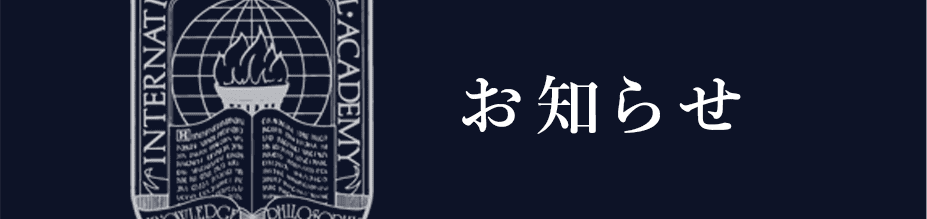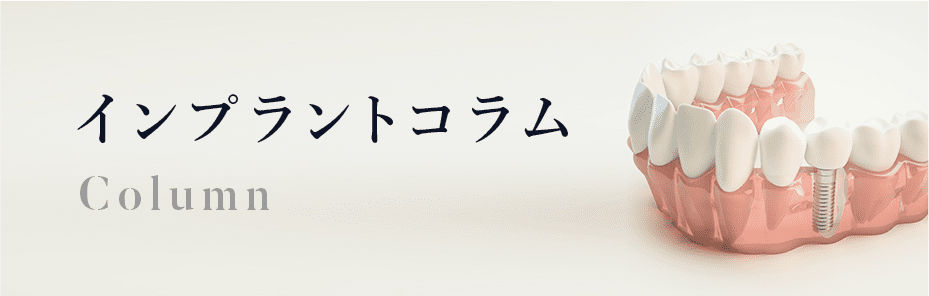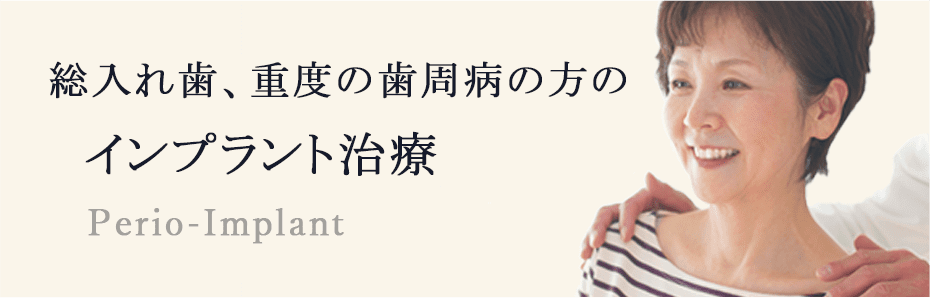インプラントコラム
COLUMN
歯周病が悪化している時にできる?歯科で行う再生治療とは
25.01.29
大切な歯をいつまでも健康に維持したい方が多いですが、歯周病やむし歯、加齢などで歯を維持することが難しくなる場合があります。
削った歯を治療はできますが、元には戻りませんし、歯周病が悪化すると顎の骨を溶かして自然に戻ることは難しくなります。
また、加齢でも徐々に顎の骨や歯ぐきが減少する場合があります。
そこで今回は、歯科で行う再生治療について詳しくご紹介します。
※お口の状況によっては適用にならない場合もあります。
歯周組織再生治療
歯を支えている歯周組織は、歯周病や加齢などで減少してしまうことがあります。
そのため、歯がグラグラするなど機能的な面でも問題が生じますが、歯が長くなるなど審美的な見た目も気になる場合があります。
そのような状態の時に、歯周組織の再生を促す歯周組織再生治療が検討されます。
・エムドゲイン
エムドゲイン法は、特殊なたんぱく質の薬剤を使用して、再生を促進する治療です。
まず、歯ぐきを切開して、歯の周りに付着した歯石や歯垢を徹底的に除去します。
そして、エムドゲインを患部に入れて、縫合して歯周組織の再生を促します。
エムドゲイン法は外科手術が1回のため、患者様の負担が少ない方法ですが、保険適用にならないため、費用の負担があります。
また、お口の状況によっては適用が難しいこともあるため、希望する方はエムドゲインが適用になるか検査する必要があります。
・リグロス
リグロスもエムドゲインと同様に、歯周組織の再生を促進することを目的にしています。
大きな違いとしては、リグロスは保険が適用になるため、費用の負担を軽減することができます。
ただし、臨床実績にも違いがあり、エムドゲインは30年前から様々な場所で、臨床で使われており豊富な臨床結果があります。
一方、リグロスは比較的新しい治療のため、十分な臨床結果が得られていない点があります。
また、成分もエムドゲインは豚の歯胚から抽出したたんぱく質を使用していますが、リグロスはヒト由来の成長因子を使用しています。
適用症例
リグロスはすべての方に適用できる治療ではありません。
リグロスは液状になっているため、歯周組織の状態が全周で失われている場合はリグロスが定着しにくいため、適用外になります
また、多くの骨が失われている場合も同様に薬剤が定着しにくいため、治療の効果が見込めません。
エムドゲインもリグロスも治療を行う前に適用を診断してから治療を行います。
・GTR
GTR法は、自家骨や骨充填剤を充填して、メンブレンという膜で覆って、失われた歯周組織を再生させる方法です。
従来のメンブレンは歯周組織の再生を確認すると、取り出す必要がありましたが、吸収性のメンブレンも選択できるようになり、治療の負担を軽減できるようになりました。
そのため、以前は2回手術が必要だったのですが、吸収性のメンブレンを使用すると、1度の手術で治療ができます。
悪化した歯周病で失われた歯肉の再生を促す方法
重度の歯周病は、歯を支えている組織や顎の骨を溶かしてしまいますが、それに伴って歯ぐきも退縮します。
そうすると、歯が長くなったように見えたり、本来であれば歯ぐきで覆われている部分が露出したりしてしまうため、しみやすくなる場合もあります。
そのような状態の時に、歯ぐきの再生を促す方法が結合組織移植(CTG)と遊離歯肉移植(FTG)です。
・結合組織移植(CTG)
結合組織移植(CTG)は、歯周病がかなり悪化して、歯ぐきの退縮がみられる時に行う治療です。
上顎の口蓋部分から、組織を採取して失われた歯ぐきの部分に移植する手術です。
知覚過敏の症状の緩和や審美性の改善が見込めます。
・遊離歯肉移植(FTG)
歯ぐきが退縮している部分に対して移植する点は、結合組織移植(CTG)と同じですが、結合組織だけでなく、表面の歯肉も移植する方法です。
歯周組織再生治療の長所
歯周組織再生治療の長所は、歯周組織が再生して歯周ポケットの深さが改善するため、歯周病の安定が見込めます。
歯周ポケットが深いと、その部分に汚れが残りやすく、歯周病の悪化するリスクが高まります。
歯周組織再生治療を行うことで、審美的な見た目はもちろん、機能面でもメリットがあります。
また、歯ぐきが覆っている部分に移植することで、知覚過敏の症状が緩和します。
歯周組織再生治療の短所
歯周組織再生治療は、大幅の骨が減少している場合や治癒が見込めない場合は治療が難しいことがあります。
また、歯周病の改善が見込めますが、清掃状況が悪いまま放置されていると、再度歯周病が悪化する可能性があります。
そのため、歯周病を安定させるためには、毎日のセルフケアが欠かせません。
歯磨きだけでなく、歯と歯の間の汚れを取るデンタルフロスや歯間ブラシも併用しましょう。
また、定期的な検診でお口の中をチェックすることも大切です。
歯周再生治療の流れ
- 精密検査
レントゲン撮影や歯周ポケットの深さ、動揺度などを精密に検査します。
そうすることで、歯周病の進行状態を把握することができます。
- お口の中の歯石・歯垢を除去する
歯周再生治療をする前に歯石や歯垢を除去して、セルフケアを十分に行い、細菌感染しにくい状態にします。
汚れが残っていると、傷口から細菌感染しやすくなってしまうため、すべての歯石や歯垢を取り除きます。
- 再評価
歯周ポケットや歯ぐきの状態を検査して、歯周病の状態を確認します。
- 歯周組織再生治療の実施
お口の状態に合った歯周組織再生治療を実施します。
- 再検査
傷口が治って症状が安定しているか確認します。
- 定期的な検診
定期的な検診で、治療した部分の歯周ポケットや歯ぐきの状態を確認し、安定しているか確認します。
【まとめ】
歯周病が悪化すると、歯がグラグラして抜け落ちてしまうこともあります。
そのため、歯周組織再生治療などを行い、できるだけ歯を維持できるようにすることも選択できます。
ただし、すべての方に歯周組織再生治療が適用になるわけではなく、治療が難しい場合もあります。
歯を失った場合は、インプラント治療も選択肢の1つになります。
当院では数多くのインプラント治療を行っていますので、インプラントをご希望の方はお気軽にご相談ください。