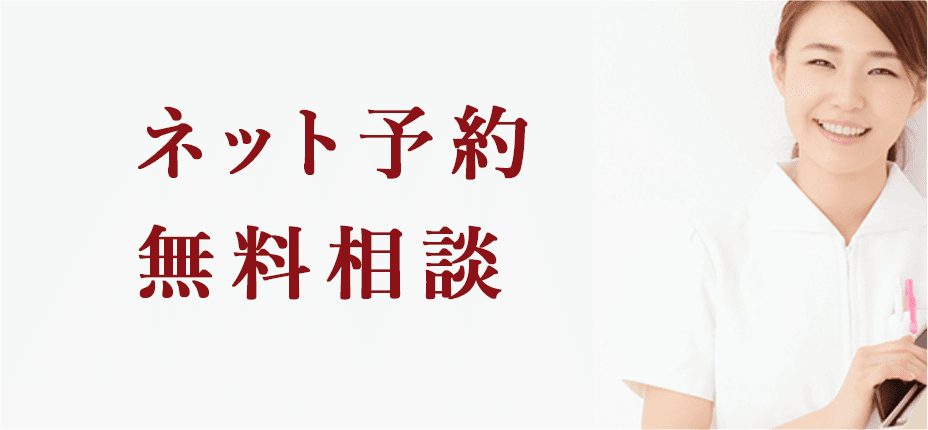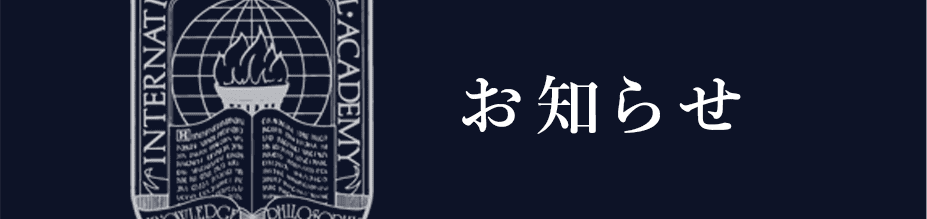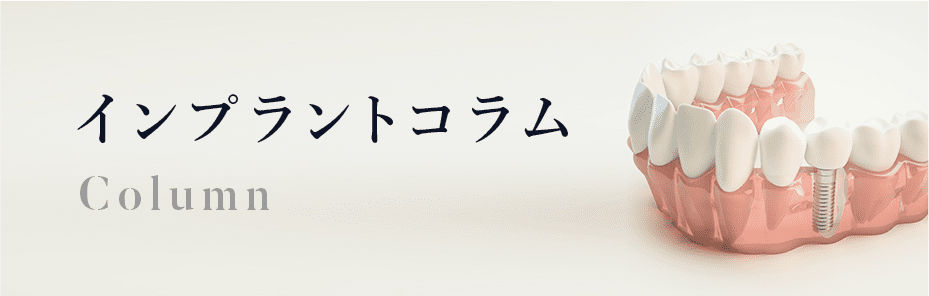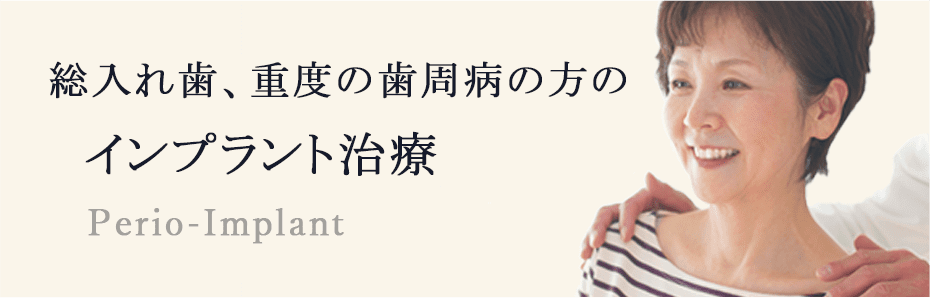インプラントコラム
COLUMN
インプラント周囲炎になりやすい人の特徴と今日からできる予防ケア
25.10.31
インプラントは、見た目も自然で天然歯のような噛み心地を実感できることから「第二の永久歯」とも呼ばれる治療法です。
しかし、埋入後のセルフケアやメンテナンスを怠ると、インプラントの周囲に炎症が起こる「インプラント周囲炎」を発症する可能性があります。
インプラント周囲炎は進行すると骨が溶け、最悪の場合にはインプラントが抜け落ちてしまうケースもあります。
そこで今回は、インプラント周囲炎の主な原因やリスク要因、日常で行えるセルフケア、そして歯科医院での定期的なメンテナンスの重要性について解説します。
インプラント周囲炎とはどんな病気?

インプラント周囲炎とは、インプラントを支えている歯周組織や骨に炎症が起こる病気です。
症状は歯周病に似ていますが、インプラントには天然歯のような歯根膜が存在しないため、炎症が直接骨へ広がりやすく進行が早いという特徴があります。
初期段階では、歯ぐきの腫れや歯磨きの時の出血などの軽い症状が見られます。
この時点で適切にケアすれば治癒しますが、放置すると炎症が骨にまで広がり、インプラントを支えられなくなる可能性があります。
そのため、インプラント周囲炎は早期発見と早期対応が、インプラントを長持ちさせるための重要なポイントです。
インプラント周囲炎の主な原因とリスク要因

・プラーク(歯垢)の蓄積
インプラント周囲炎の直接の原因は、プラーク(歯垢)に潜む細菌です。
インプラントは天然歯よりも清掃が難しく、歯ブラシが届きにくい細部に汚れが残りやすい傾向があります。
特に、人工歯と歯ぐきの境目に細菌がたまると、炎症を引き起こしやすくなります。
・定期的なメンテナンスの不足
治療後の定期的なメンテナンスを怠ることも大きなリスク要因です。
インプラントは「被せ物が入ったら終わり」ではなく、年に数回のプロケア(歯石除去・咬合チェック)が必要です。
不具合が起きる前に早期発見・対処することでインプラントを維持しやすくなります。
通院を後回しにすると、気づかないうちにインプラント周囲炎が進行してしまうことがあります。
・噛み合わせの不調や過度な力
咬み合わせのズレや特定の歯に集中する過度な力も、インプラント周囲炎を悪化させる原因の一つです。
インプラントと骨に負担がかかることで、炎症や骨吸収が進行してしまう可能性があります。
特に歯ぎしり・食いしばりのある方は、ナイトガードなどによる対策が推奨されます。
・喫煙・糖尿病・ストレスなどの全身要因
喫煙によって血流が悪くなると、酸素が十分に行き渡りにくく、治癒力が低下し感染リスクが高まります。
また、糖尿病や慢性的なストレスによる免疫力の低下も炎症のリスクが高くなります。
そのため、インプラントを維持するためには、全身の健康管理も重要なポイントです。
インプラント周囲炎を放置するとどうなる?

インプラント周囲粘膜炎(初期段階)
歯ぐきに軽い腫れや歯磨きの時の出血、口臭などが見られます。
痛みはほとんどなく、自覚症状が少ないため気づきにくい状態です。
インプラント周囲炎(中等度)
歯周組織の炎症が進行し、骨の吸収が始まる段階です。
レントゲンではインプラント周囲に黒い影が確認され、歯ぐきの退縮や膿が出る症状が見られることもあります。
重度インプラント周囲炎(重度)
炎症がさらに進むと、インプラントがグラグラし、最悪の場合は脱落してしまうこともあります。
再治療を行う場合はそのままの状態では難しく、骨造成(GBRなど)が必要になるケースもあります。
早い段階で発見できれば、専門的なクリーニングや歯石除去で改善が見込めます。
「痛くないから大丈夫」と放置せず、出血・腫れ・口臭などの小さな変化の時が受診のサインと考えましょう。
自分でできるセルフケアのポイント
ブラッシングは「やさしく」「丁寧に」
歯ブラシは毛先のやわらかいタイプを選び、歯ぐきの境目の周りを小刻みにやさしく磨くのがポイントです。
インプラントは天然歯と形が異なるため、タフトブラシ(先端の細いブラシ)やスーパーフロスを併用すると、歯ブラシが届きにくい部分の清掃にも効果的です。
生活習慣を整えて炎症を防ぐ
喫煙、過度な飲酒、睡眠不足は歯ぐきの免疫力を低下させ、炎症を悪化させる要因になります。
日常の食事では、ビタミンCやタンパク質を意識して摂取し、歯ぐきや骨の健康維持をサポートしましょう。
体の内側と外側の両面からケアを続けることが、インプラントを長く守るポイントです。
洗口液を取り入れる
インプラント周囲の細菌バランスを整えるために、クロルヘキシジン配合の洗口液を活用するのがおすすめです。
歯科医院で行うメンテナンス

インプラントを長期的に安定させるためには、定期的なメンテナンスが重要です。
セルフケアだけでは届かない汚れや噛み合わせのバランスの確認を、歯科医院でしっかりコントロールしていきます。
定期検診
歯ぐきの状態・出血の有無・ポケットの深さなどを確認し、必要に応じてレントゲンで骨の変化もチェックします。
炎症が軽度であれば、チタンチップ付きの超音波スケーラーなど専用の器具で汚れを取り除くだけで改善が見込めます。
噛み合わせの再調整とナイトガードの活用
咬み合わせに変化が見られた場合は、早めの調整でトラブルを予防します。
また、夜間の歯ぎしり・食いしばりがある方には、ナイトガード(マウスピース)を装着することでインプラントや骨への負担を軽減できます。
【まとめ】
インプラント周囲炎は、一度治っても再発するリスクが高い病気です。
だからこそ、「治療」よりも「予防」や「維持」が大切になります。
・3〜6か月ごとの定期メンテナンス
・咬合チェックとクリーニング
・生活習慣・全身管理の見直し
この3つを継続することで、インプラントを長く維持しやすくなります。
インプラント周囲炎は、正しいケアと早期対応で防げる病気です。
そのためには毎日のセルフケアに加えて、歯科医院による定期的なメンテナンスを欠かさないことが大切です。
「インプラントの周りが腫れている」「歯みがきのたびに出血する」そんなサインがある方は、早めに歯科医院で診察を受けましょう。